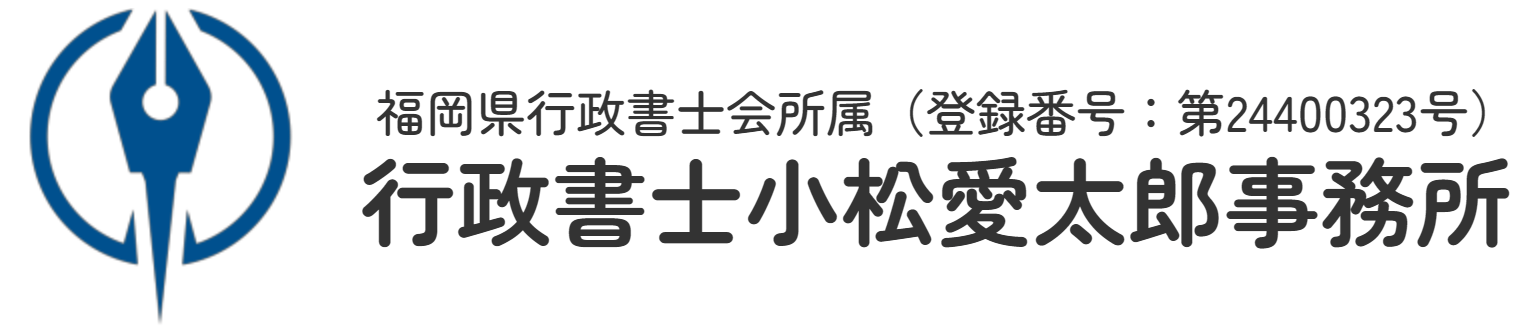【緊急】建設業許可を取るための事務所とは(令和7年10月改訂)
今回は番外編です。
10月15日付で、福岡県HPにおいて「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」が公表されました。
新たに規制が厳しくなった訳ではないですが、建設業許可を取るための営業所の要件が「厳格化」されました。
今回はこちらについて解説したいと思います。

<営業所をクリアするための主なポイント>
- 建設業の請負契約の締結に関する実体的な行為事務所であること
- 事務所としての形態があること(固定電話、机、各種台帳の保管場所等)
- 独立性が保たれていること
- 営業所の使用権原を有していること
- その他、法令を遵守していること
【以前の記事はこちら】営業所技術者(旧:専任技術者)とは|建設業許可を取る方法(応用編)
【建設業許可取得のご相談はこちらから】福岡県で建設業許可を取るなら|建設業許可 福岡サポートオフィス
福岡県の審査部署においては、以下の視点で審査をすると明示されております
・外部からの来客を迎え入れて請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行えるか
そもそも、建設業許可で定義されている営業所とは、どんな建物でも認められる訳ではありません。
その1つが「建設業の請負契約の締結に関する実体的な行為事務所であること」が必要です。
「建設業許可で求められる営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、協議の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約の名義人が当営業所を代表する者であるか否かを問いません。
福岡県の審査部署においては、以下の視点で審査をすると明示されております
・営業所の入口が来客等の第三者に容易にわかる構造であるか
・社会通念上、事務所として見なすことができる設備・備品を備えているか
・机(○台)、応接設定(有・無)、固定電話(有・無)、パソコン(有・無))
・建物の形態(店舗型・戸建住宅・集合住宅・プレハブ等)
・プレハブの場合、面積は何㎡か
次は事務所内の備品や設備についてです。
契約を締結する場所でないとならないので、もちろん机や応接セットがないと不自然です。
また、本当に営業所として機能しているのか問われるため、固定電話(携帯は不可)・パソコン・書類の保管場所(書庫など)は必要です。
プレハブを事務所にする場合については、後半でも触れますが、色々と注意が必要です。
福岡県の審査部署においては、以下の視点で審査をすると明示されております
・他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれているか
・<動線>居住部分や他者(他社)の部分を通らずに自社の事務所に直接入れるか
・<間仕切り>居住部分や他者(他社)の部分と壁や間仕切り等で明確に区画されているか
・<事務所表示>事務所の入口に事務所名が記載された表札や案内板があるか
・<生活感>事務所内に個人の生活用品がなく事業専用の場所になっているか
住居とは別に、専用の事務所を借りる場合は問題ないですが、
よくあるケースとして、自宅を事務所として登録する際は、上記のとおり注意が必要です。
この点で苦慮されて許可を取るのに二の足を踏んでいる方が多い印象です。
福岡県の審査部署においては、以下の視点で審査をすると明示されております
・営業所の使用権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しているか
・営業所として使用することについて所有者等からの承諾を得られているか
・分譲マンションの一室を営業所にする場合、管理組合の同意を取ること
・賃貸借契約書の使用目的が「事業用」になっているか
・賃貸借契約書の使用目的が「居住用」の場合、別途「使用承諾書」を所有者からもらうこと
審査の際には、上記を客観的に照明するため、賃貸借契約書や同意書・承諾書の提出も必要です
福岡県の審査部署においては、以下の視点で審査をすると明示されております
・建設業法第40条の3に基づく帳簿の備付け・保全及び営業に関する図書の保存を遵守しているか
・労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」を遵守しているか
・建築基準法を遵守しているか
・プレハブやコンテナ等を設置し事務所として使用する場合、建築基準法上の建築物とするため、原則として建築確認申請が必要
・建築物は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結する必要があります。プレハブやコンテナ等がブロックに乗せただけになっている場合、確認申請を受けていない場合は、建築基準法に適合していない可能性がありますので、建設業許可申請とは別途、建築基準法関係部署へご相談ください
上記の通り、プレハブやコンテナを事務所として登録する場合は、注意が必要です。
<さいごに>
今回は番外編になりましたが、建設業許可を取るための営業所について解説しました。
当事務所では、福岡県を中心に、建設業の許可申請を専門の行政書士が代行しております
ご質問にも丁寧に対応しております。以下のフォームよりお気軽にお問合せください。